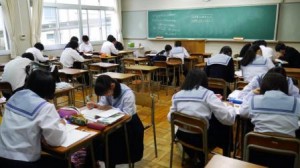学校の周りでは、桜が満開の花を咲かせました。まさに春爛漫です。今日から新たな1年を始める皆さんに、激励のエールを送っているかのようです。
平成27年度1学期の始業に当たり、私も激励の気持ちを込めて2つの話をしたいと思います。
******************************
蓋のある「箱」の中に、いくつかの「大きな石」と多くの「小さな石」、そして「砂」を入れる作業をするとします。何を、どんな順序で「箱」に入れますか。
普通は、先ず「大きな石」を入れ、その隙間に「小さな石」を入れ、最後に「砂」を入れます。逆に、最初に「砂」を入れてから「小さな石」を入れ、最後に「大きな石」を入れると蓋ができなくなるかもしれません。
これは、「大事なものを先にする」ことの例としてよく引用される話です。「箱」が「自分の時間」、「石」の大きさが「やるべきことの重要度」を表し、優先順位の決め方によって結果が違ってくることを意味しています。
具体的に考えてみます。例えば、「仕事と勉学を両立させてみせる」と決意した人は、一時間、一時間の授業を大切にするでしょう。仕事も意欲的に取り組めるはずです。また、帰宅後の就寝までの時間をどう使うべきか、その術を身に付けていなければなりません。LINEの「既読」メッセージなどに振り回されることもありません。
このように、「他のことより大事にしていること」があるかどうか、これが大きな違いを生みます。それを持っている人は、時間の使い方などに迷いがありません。少々のことは我慢できるはずです。
逆に、「大事にしていること」を持っていない人は、その時の気分や感情、その場の雰囲気に振り回され、やりたいと思ったことに時間を使い、その場で欲しいと思った物に金を使ってしまいます。その結果、「なりたい自分」にはなかなかなれませんし、本当に必要なものを手に入れることもできません。
中心が決まれば、周りのことは自ずと決まっていきます。目的が明確であれば、手段も絞られます。
皆さんは、高校生活という「箱」の中に、どんな「大きな石」を入れたのでしょうか。学年が一つ上がった今、自分の「箱」に「大きな石」を入れ直したという人もいるかもしれません。それも良いと思います。
「大きな石」こそ、成し遂げようとする「固い意志」、すなわち「志」です。「志」をブレずに貫こうとする皆さんの努力に期待したいと思います。
******************************
次に、Never give up!という話です。「これはとても無理だ。自分にはできない。」というふうに、簡単に諦めてはいけないということです。
私たちは、「できること」は簡単に証明できます。やってみせさえすればよいからです。しかし、「できないこと」は簡単には証明できません。何故なら、10回できなくても11回目で、100回できなくても101回目でできるかもしれないからです。
そうすると、ある人はこんな反論をするかもしれません。「何回も挑戦できるのなら簡単には諦めないけれど、チャンスは1回限りという場合は諦めが肝心ということもある。」なるほど、そういうこともあるでしょう。
先生方の力を借りましょう。ここにいる先生方は、皆さんの最大の応援団です。
学校というところは「学ぶ」ところです。「学ぶ」ということは、「変わる」ということです。「できないこと」を減らし、「できること」を、先生方の力をかりながら、どんどん増やしていってください。そうすれば、自分ひとりの力で、チャンスは1回限りという場合でも、自分一人の力で挑戦できるようになるはずです。
頑張れ、上高生。皆さんの「大いなる挑戦」に期待し、1学期始業式の話を終わります。
2015年4月8日 東 則尚




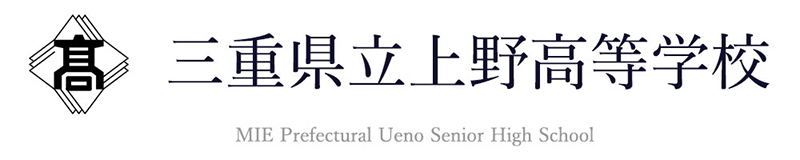
 続々と登校してくる生徒たち。朝早くから来て勉強を始めている生徒もいます。
続々と登校してくる生徒たち。朝早くから来て勉強を始めている生徒もいます。