| 東紀州地域 |
|---|
 三重県立熊野青藍高等学校(全日制)
三重県立熊野青藍高等学校(全日制) |
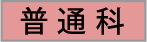
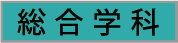
-
 木本校舎
木本校舎 紀南校舎
紀南校舎 -
所在地 (木本校舎)
〒519ー4394
熊野市木本町1101-4
(紀南校舎)
〒519-5204
南牟婁郡御浜町阿田和1960交通機関等 (木本校舎)
JR紀勢本線熊野市駅下車約1km
(紀南校舎)
JR阿田和駅下車約1.5km
三交バス「御浜町阿田和」下車約700m
全校生徒数 (木本校舎) 152名
(紀南校舎) 31名 (令和7年5月1日現在)制服 あり 始業時間 (木本校舎) 8時45分
(紀南校舎) 9時05分連絡先 (木本校舎) 0597-85-3811
(紀南校舎) 05979-2-1351URL https://sites.google.com/mie-c.ed.jp/kumanoseiran E-mail (木本校舎)
hkimotad★mxs.mie-c.ed.jp
(紀南校舎)
hkinanad★mxs.mie-c.ed.jp
※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えてください。
基本理念
持続可能な社会の一員として、ふるさとを想い、未来に希望を持って幸福を実現する人材を地域とともに育てる「開かれた学校」
・自己肯定感を高め、夢や目標の実現に向けて主体的に学び続ける生徒
・人との出会い・つながりを大切にし、互いのよさを生かして協力・協働する生徒
・自分の可能性を信じ、何事にも積極的に挑戦し未来を切り拓くことができる生徒
学校の特色
(1)普通科(特進コース・普通コース)
入学時から教育課程が異なる2つのコースに分かれ、希望する進路に応じた教科を学びます。3年間を通じて、国語、数学、英語、地歴・公民、理科等の「共通教科」を重点的に学習します。授業はもとより放課後や長期休業中の補修の充実により、各自の興味・関心に応じた学びを深めます。三重大学や地域との連携を進め、探究的な学びを充実させることで、多様な入試形態に対応します。勉強と部活動の両立を図ることを考え、7限授業は両コースの全学年とも週1回実施します。
(2)総合学科(情報ビジネス系列・リベラルアーツ系列)
「産業社会と人間」や「総合的な探究の時間」などにおいて、地域社会の課題解決をめざす探究活動「東紀州未来学」に取り組みます。2年生以降は2つのコースに分かれて、多くの専門科目や学校設定科目を含む多彩な選択科目群から、自己の興味・関心や進路希望等に応じて科目を選択して学べます。木本校舎・紀南校舎の合同発表会等により互いの学びの成果を共有するとともに、仲間とのつながりを広げ深めます。
●総合学科(地域デザイン系列・産業マイスター系列)
単位制を導入し、四年制大学への進学をはじめ、多様な進路希望のニーズに対応するために、2年次以降は『総合進学コース』『医療・看護コース』『福祉コース』『ビジネスコース』『コミュニケーションコース』の5つのコースに分かれ、学習を進めます。自分の進路や興味・関心に応じた授業を選択することで、様々な資格の取得にも積極的に挑戦していきます。また、1年次から「産業社会と人間」や「総合的な探究の時間」等において、地域社会の課題解決をめざす探究活動「東紀州未来学」に取り組むとともに、進路について考える時間を十分に確保し、生徒の皆さんが将来の職業などを意識できるように取り組むことで、進路実現を支援していきます。さらに、木本校舎との合同発表会等により互いの学びの成果を共有し、仲間とのつながりを広げ深めます。
※系列やコースに関係なく、選択授業を選ぶことができます。
●2年次に選択科目『就労体験(6単位)』(長期インターンシップ)を実施
本校では、生徒の皆さんが、将来、社会的・職業的に自立できるよう、3年間を通じたキャリア教育を重視しています。特に、2年次生が対象の「就労体験」(長期インターンシップ)では、地元の様々な職場で、毎週1日、就労体験を行っています。この体験をとおして、勤労観や職業観の醸成や異世代とのコミュニケーション能力の向上を図っています。就労体験を選択した生徒からは、「就労体験をしたことで進路目標が明確になった。」「自分で考え行動することができるようになった。」「自分に向いていることや、できることをしっかり知ることができた。」といった感想が聞かれ、大変好評です。
学校PR
【木本校舎】
入学後、早期からの進路指導を重視しています。個別面談を通して学習意欲を高めながら、授業で基礎学力をつけることによって、すべての生徒のレベルアップを図っています。
また、家庭との連携のための保護者面談や家庭訪問を実施したり、個人データの分析を的確に行ったりするとともに、年間を通して計画的な課外授業を行っています。
部活動については、どの部も県大会で上位をめざして頑張っています。入部率はおおよそ8割と、多くの生徒が部活動に取り組んでいます。
【紀南校舎】
熊野青藍高校紀南校舎は、保護者の方や地域の皆さんの意見を学校運営に取り入れたり、地域の皆さんから様々なことを学ぶ機会を設けたりすることで、これからの地域社会で活躍できる人材の育成を進めています。特に、「主体的・対話的で深い学び」の実践に日々努めるとともに、部活動、生徒会活動、ボランティア活動などを活発に行い、これからの地域社会で生かせる能力の習得につなげています。地域の活性化に取り組んだり、防災学習を実施したりして、地域を学びのフィールドとした教育に力を入れています。
-

この高校の回答一覧へ
今までの回答と質問です -

質問コーナーへ
回答は高校Q&Aに掲載されます。