2016年度対面式
4月11日(月)の午前に対面式が行われ、在校生が新入生324名を歓迎しました。
生徒会会長の歓迎の挨拶、新入生代表挨拶、生徒会執行部による学校生活の紹介と続き、最初緊張した新入生も式が進むにつれ、笑顔も見られました。
(生徒会会長挨拶)

(新入生代表挨拶)





2016年度対面式
4月11日(月)の午前に対面式が行われ、在校生が新入生324名を歓迎しました。
生徒会会長の歓迎の挨拶、新入生代表挨拶、生徒会執行部による学校生活の紹介と続き、最初緊張した新入生も式が進むにつれ、笑顔も見られました。
(生徒会会長挨拶)

(新入生代表挨拶)

始業式が昨日あったばかりですが、今年度の高校テニス競技が始まりました。
県総体の予選が4月9日にダブルス・4月10日にシングルスが各高校で開始されました。
上高女子テニス部は、白子高校、津商業高校、セントヨゼフ女子学園等に分かれ、予選を戦いました。ダブルスでは、惜しくも敗退しましたが、シングルスでは、一人勝ち抜きました。4月30日にスポーツの杜鈴鹿で開かれる本戦に出場します。
また、5月28日からは団体戦がスポーツの杜鈴鹿で行われます。応援をお願いします。
白子高校会場での集合 試合開始


2016年度入学式
4月8日(金)の午後に入学式が行われ、新入生324名の入学が許可されました。

高校生活への期待・不安が混じった様子で、緊張が張りつめた入学式となりました。

春の風が学校に花の匂いや鳥のさえずりを運んでくれる今日の良き日、御来賓の皆様、入学生の保護者の皆様の御臨席のもと、平成28年度入学式を執り行うことができますことは、私共のこの上ない喜びであり、誠に嬉しく存じます。本校を代表し、深く感謝申し上げます。
本校の校門をくぐった新入生のみなさん、入学おめでとうございます。心から歓迎いたします。
保護者の皆様、お子様の御入学、誠におめでとうございます。これまでお子様を育ててこられました皆様の御尽力に衷心より敬意を表すとともに、お子様に寄せる思いを真摯に受け止め、私共教職員は、お子様の大いなる成長を目指して教育活動に取り組んでまいります。どうか、本校の教育活動に御理解、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
さて、新入生の皆さん。皆さんは、今日から高校生として新しい生活に入ります。期待に胸を躍らせながらも、不安も感じていることでしょう。安心して心を開いてください。そして、分からないことは何でも尋ね、早く上野高校に慣れてください。
皆さんの中には、高校進学を機に、自分を変えたいと思っている人もいるでしょう。何かに反発して荒れた生活を送っていたという人や、あまり学校には行けなかったという人もいるかもしれません。これまではどうであれ、リセットすればよいのです。そして今は、夢に向かって挑戦できることに感謝しましょう。今の自分の状況に先ずは感謝です。その上で、「4年間、本当によく頑張った。今があるのは、その時の努力のおかげです。」と、5年後、10年後の自分から感謝されるような高校生活を送ってください。これから過ぎ去っていく過去は、皆さん自身の手でどのようにも作り上げることができます。今の皆さんには、自分の将来を決めるだけの可能性と力を持っています。今日からの一日一日がどれだけ価値のあることか、しっかりと今の自分の中に刻み込んでほしいと思います。
そこで、こんな話をしたいと思います。皆さんも知っているように、オタマジャクシは、やがてカエルになります。尻尾が消え足が生え、陸に上がって飛び跳ねることができるようになります。しかし、カエルになれるのなら、カメにもなれるかというと、そうはいきません。カエルにしかなれないのです。オタマジャクシがカエルになること、それは、「より自分らしくなる」ということです。ここに成長のあるべき姿をイメージしてほしいと思います。
また、青虫はさなぎになり、そして蝶になります。この姿にも自分の成長をイメージしてください。青虫のあいだは思うように動けず、とても不自由な身です。しかし、さなぎを経て蝶になると、羽が生え、自由に飛び回れるようになります。「這う世界」から「飛ぶ世界」への変化です。しかし、トンボにはなれません。蝶にしかなれないのです。ここで悩んでしまうのではなく、羽が生えて飛べるようになることを喜ぶべきなのです。それが、「最も自分らしく輝いている姿」なのです。
皆さんの中に、他人との比較が癖になって自己嫌悪に陥り、今の自分を捨てて別人になろうともがいている人はいないでしょうか。言わば「自己否定の罠」にはまっている人です。憧れている誰かと比較し、嫌いな自分を消し去ろうとしたり、自分を捨てて別人になろうとしたりしてはいけません。「ダメな自分」「情けない自分」をあぶり出して、自己嫌悪に陥るのではなく、「ありのままの自分」を受け入れ、そういう自分と向き合い、つき合っていけば、これが自分本来の姿だと思う時があるはずです。それが本当の「自分らしさ」だと思います。
「自分らしさ」は、親から授かった自分に与えられた能力・個性です。それを一生懸命に磨き続けていると、「自分本来の姿」に変身できるのです。それまでは、ごちゃごちゃ言わずに自分を磨き続けなければなりません。これが中途半端だと、オタマジャクシとしては成長できたとしてもカエルにはなれません。自分磨きを途中で怠ると、大きな青虫になれても蝶には変われません。自分に与えられた能力・個性を進化させるところまで磨き続けることが大事なのです。
それでは、どのように自分を磨き続けていけばよいのでしょうか。私たちには、「しなければならないこと」「したいこと」「できること」の3つがあります。「したいこと」を我慢し、「しなければならないこと」だけをする、そんな生活が続くと、一向に自分の夢や希望に近づいていないように感じ、「このままでいいのか、こんなはずじゃない」と思いがちです。しかし、実はそうではありません。逆に、「しなければならないこと」を脇に追いやり、「したいこと」だけをしていると、いつまでたってもオタマジャクシや青虫のままで、成長は望めません。「できること」も増えていきません。
皆さんが、上野高校で、「しなければならないこと」と「したいこと」の両方をうまく両立させ、自分らしく、大きく成長することを期待します。
最後になりましたが、御多用の中、御臨席賜りました御来賓の皆様方に、心から御礼申し上げます。これからも、本校に対し、一層の御支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
待ちわびた春は希望の春。新入生12名の大いなる成長を祈りつつ、式辞といたします。
アメリカのペンシルバニア州に、イタリアからの移民がつくったロゼトという町があります。この町では1950年代に、医学的に大変不思議な現象がみられました。心臓疾患の危険因子である喫煙、肥満、糖尿病、動物性脂肪の摂取量は他の町の住民と変わらないのに、ロゼトでは心臓疾患による死亡率が他の町よりも極端に低かったのです。「ロゼトの奇跡」と言われ、研究者の注目を集めました。その理由を探ろうと様々な調査が行われましたが、結局分かったことは、他の町と比べて「住民同士のつながりが強い」ということでした。何があっても周りが助けてくれるという安心感が心臓疾患を減らしていると研究者たちは考えたのです。ところが、時代が進み、ロゼトの住民同士の連帯感が弱まるにつれて、心臓疾患による死亡率も他の町と変わらなくなったそうです。
私たちは毎日、互いに頼ったり、頼られたりして暮らしています。時には迷惑をかけたり、迷惑をかけられたりもします。このような双方向の関係を嫌がり、過度な自立意識を振りかざして強がっていては連帯感など生まれません。パソコンやスマホが普及して、隣で仕事をしている同僚に口で言えばよいのにメールで用件を伝えるとか、1年経ても名前の分からないクラスメートがいるとか、人間関係の在り方が徐々に変化してきている例は枚挙に暇がありません。
前任校でのことです。中学までは聾学校で学び、高校は高校野球がしたいと前任校に進学した聴覚障がいを持つ生徒がいました。耳は全く聞こえません。彼のために前任校の生徒たちと先生方は何をしたか。野球部員は練習や試合で彼と意思疎通ができるよう「指言語」を覚え、クラスメートは文化祭の舞台発表で彼を中央に立たせて手話パフォーマンスを演じ、先生方は当番表を作って授業中に彼の隣で交代でノートを取りました。彼は、卒業式の答辞で、「この学校で最高の高校生活を送ることができた」と感謝の言葉を手話で表現しました。
私たちの日常には、「あなたのおかげで助かった。」「あなたがいるので何とかやっていける。」と言い合える関係がもっとあってもよいのではないか。当たり前のように助け合い、つながり合い、共に生きていく力、すなわち、共生社会を築いていく力こそ、今求められる「生きる力」だと、東日本大震災から5年経った今、改めて言いたいのです。
そのためにはどうすればよいか。先ずは、人が捨てたゴミを拾う。老人に電車の席を譲る。先に道を譲る。段差で動けない車椅子の人に手を差し伸べることです。これらのことは、「何故、私がこんなことをしなければならないのか。」という気持ちを乗り越えなければできないことです。「何故、自分だけが」という気持ちがある限り、他者とつながり合うことなどできません。
学校も同じです。学校行事等では、「自分の役割」と「他者の役割」の隙間にある「誰の仕事でもない仕事」は最初に気づいた者がする。「自分の仕事」なのか「他者の仕事」なのか判断に迷う仕事はさっさと引き受ける。これが共生社会の基本ルールだと思います。「自分のために」から「誰かのために」、「皆のために」へと考え方を転換し、「他者の幸せは自分の幸せ」と考える人が増えていけば、「孤立」に陥る者などいるはずはなく、「依存」から「共存」へ、そして「自立」へという道筋のなかで、一人ひとりが「生きる力」を身に付けていくのだと思うのです。
皆さんは今日から、新しい学年で学校生活を始めます。普通科の皆さんは新しいクラスメートと出会い、理数科の皆さんも気分一新で今日を迎えたことと思います。この一年は最高の一年だった、このクラスは最高のクラスだったと振り返ることができるよう、互いに助け合い、励まし合い、絆の強いクラスやクラブを作っていってください。
以上で前期始業式の話を終わります。
柔らかな春の光に包まれ、木々の新芽に生命の躍動を感じる今日の良き日、御来賓の皆様、入学生の保護者の皆様の御臨席のもと、平成28年度入学式を執り行うことができますことは、私共のこの上ない喜びであり、誠に嬉しく存じます。本校を代表し、深く感謝申し上げます。
上野高校の制服を着て本校の校門をくぐった新入生のみなさん、入学おめでとうございます。皆さんは、義務教育を終え、今日から高校生として新しい生活に入ります。期待に胸を躍らせながらも、不安も感じていることでしょう。しばらくの間、落ち着かない日々が続くと思いますが、心を開いて分からないことは何でも尋ね、早く上野高校に慣れてください。
皆さんは、御家族や中学校の先生方のサポートがあったにせよ、最終的には自らの責任で高校進学を決められたことと思います。高校では、国民の義務としての教育状況から大きく変化し、自己責任に裏打ちされた行動が求められます。その時、その場で、何をすべきで何をすべきでないのか、どうすることが適切なのか、自分で考え、判断し、自主的・主体的に行動する力を身に付けていってください。
保護者の皆様、お子様の御入学、誠におめでとうございます。これまでお子様を育ててこられました皆様の御尽力に衷心より敬意を表すとともに、私共教職員に課せられた責任の重さに身の引き締まる思いでございます。お子様に寄せる思いを真摯に受け止め、私共は、お子様の大いなる成長を目指して教育活動に取り組んでまいります。どうか、本校の教育活動に御理解、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
さて、新入生の皆さん。皆さんにお願いしたいことがあります。それは、「夢の実現に向けた自分の決意を表明する儀式」を自分で行ってほしいということです。物事の始まりの「節目」では「儀式」が行われます。日常生活でも同じです。毎日の挨拶、授業開始時の「起立、礼」、食事の時の「いただきます。」これらは一種の「儀式」です。スポーツ選手のなかには、練習を始める時に、自分を鼓舞するために毎回必ず同じ練習メニューを実行する選手がいるそうです。これも「儀式」です。
皆さんが本校で学校生活を始める今、「夢を実現するために必ずやること」考え抜き、自分の中で正式決定し、その決意を表明する「儀式」を自分自身で静かに、確実に行ってほしいのです。今後、挫折へと導く誘因はいくらでも出てきます。やろうとすればするほど、わざと邪魔をするかのようなことが起こるものです。そして、やがて「やる気」が削ぎ落とされ、その場しのぎの言い訳を探し出すようになってしまいます。そうならないために、触れば火傷をするくらいの気概を持って、「夢の実現に向けた決意表明の儀式」を行ってください。
そのことをお願いしたうえで、こんな話をしたいと思います。皆さんも知っているように、オタマジャクシは、やがてカエルになります。尻尾が消えて足が生え、陸に上がって飛び跳ねることができるようになります。しかし、カエルになれるのなら、カメにもなれるかというと、そうはいきません。カエルにしかなれないのです。オタマジャクシがカエルになること、それは、「より自分らしくなる」ということです。ここに成長のあるべき姿をイメージしてください。
また、青虫はさなぎになり、そして蝶になります。この姿にも自分の成長をイメージしてください。青虫のあいだは思うように動けず、とても不自由な身です。しかし、さなぎを経て蝶になると、羽が生え、自由に飛び回れるようになります。「這う世界」から「飛ぶ世界」への変化です。しかし、トンボにはなれません。蝶にしかなれないのです。ここで悩んでしまうのではなく、羽が生えて飛べるようになることを喜ぶべきなのです。それが、「最も自分らしく輝いている姿」なのです。
皆さんの中に、他人との比較が癖になって自己嫌悪に陥り、今の自分を捨てて別人になろうともがいている人はいないでしょうか。言わば「自己否定の罠」にはまっている人です。憧れている誰かと比較し、嫌いな自分を消し去ろうとしたり、自分を捨てて別人になろうとしたりしてはいけません。「ダメな自分」「情けない自分」をあぶり出して、自己嫌悪に陥るのではなく、「ありのままの自分」を受け入れ、そういう自分と向き合い、つき合い続けていけば、これが自分本来の姿だと思う時が必ず来るはずです。それが本当の「自分らしさ」だと思います。
「自分らしさ」は、親から授かった自分に与えられた能力・個性です。それを一生懸命に磨き続けていると、「自分本来の姿」に変身できるのです。それまでは、あれこれ文句を言ったり言い訳をしたりせずに、自分を磨き続けなければなりません。これが中途半端だと、オタマジャクシとしては成長できたとしてもカエルにはなれません。自分磨きを途中で怠ると、大きな青虫になれても蝶には変われません。自分に与えられた能力・個性を一生懸命に磨き続けることが大事なのです。
それでは、どのように自分を磨き続けていけばよいのでしょうか。私たちには、「しなければならないこと」「したいこと」「できること」の3つがあります。「したいこと」を我慢し、「しなければならないこと」だけをする、そんな生活が続くと、一向に自分の夢や希望に近づいていないように感じ、「このままでいいのか、こんなはずじゃない」と思いがちです。しかし、実はそうではありません。逆に、「しなければならないこと」を脇に追いやり、「したいこと」だけをしていると、いつまでたってもオタマジャクシや青虫のままで、成長は望めません。「できること」も増えていきません。
皆さんが、上野高校で、「しなければならないこと」と「したいこと」の両方をうまく両立させ、自分らしく、大きく成長することを期待します。
最後になりましたが、御多用の中、御臨席賜りました御来賓の皆様方に、高い所からではございますが、心から御礼申し上げます。本当にありがとうございました。これからも、本校に対し、一層の御支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
待ちわびた春は十五歳の希望の春。新入生324名の大いなる成長を祈りつつ、式辞といたします。
2016年度前期始業式・着任式
4月8日(金)に着任式が行われ、14名の教職員を新たにお迎えしました。

引き続き、前期始業式が行われました。
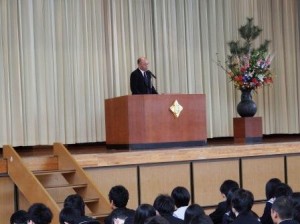
開始時間より早く整列し、気持ちの良いスタートとなりました。
2015年度の学校生活を締めくくるに当たり、今日は、私の一人の知人のことを話したいと思います。
その知人は、私が最初に勤めた高校の教え子です。教え子と言っても、50歳を超える壮年です。彼は、私が顧問をしていた運動部の部員で、1年生の時の担任も私でした。
彼が3年生の時の最後の公式試合でのことです。勝利を目前にした終盤、彼は痛恨の大きなエラーをしました。その後チームは浮足立ち、結局、我がチームは敗退しました。試合終了後、全員が泣き崩れ、それでも3年生のチームメイトは彼を抱きかかえながら声をかけていました。帰りのバスの中は、いつもなら賑やかな話し声が飛び交うはずが、誰もが沈痛の面持ちで、重苦しい雰囲気が漂いました。私も「早く学校に着いてくれ。」と祈るような気持ちだったことを今でも覚えています。実は、この痛恨のエラーが、彼のその後の人生に大きな影響を与えることになります。
昨年のある日、彼から電話がかかってきました。それまで、そのチームの同窓会が何度か開かれていたのですが、彼はほとんど出席することがなかったので、本当に久しぶりでした。転勤で故郷に戻ることになったこと、ある仕事の責任者となったことなどを話してくれました。私は、次の日に彼と会う約束をしました。
次の日の夕方、いつもより少し早く学校を出て、彼の住む町まで車を走らせました。そして、一緒に食事をしながら、彼は、その「苦い思い出」をバネにして生きてきたことを話してくれたのです。
私は、あの頃と同じように真っ黒に日焼けした顔と年齢にしては皺が多いことに驚きました。相変わらず口数が少なく、昔をしのばせる笑顔で、静かに、あの頃と同じような口調で話してくれました。私は、彼が私に連絡をくれて久しぶりに会えたことも嬉しかったのですが、一番嬉しかったのは、「あのエラーがあったから、俺はここまでやってこれたんさ。」と言ってくれたことです。かつての教え子が高校卒業後約30年の間、「苦い思い出」をバネにして強く生き抜いてきたということを知り、心の底から嬉しさを覚えました。そして、彼の部顧問、担任だったことを誇らしく思いました。
「過去に何があったか」が幸不幸を決めるのではない。悔しさをバネに前向きに生きていく。どんな辛い経験にも意味があると思える「強さ」を皆さんに持ってほしい。そんな思いで今日、知人の話をしました。
今日は、一年間の締めくくりの日です。また、本年度末の人事異動で何名かの先生方との別れの日でもあります。しっかりと一年の締めくくりをして、本校を離任される先生方を感謝の気持ちで爽やかに送り出してください。
以上で、修了式の話を終わります。
2016年3月24日(全日制)
3月22日(定時制)
東 則尚
3月20日(日)に「第18回『雪解』のつどい」がハイトピア伊賀で開催されました。
『雪解』は、上野高校の前身である旧制三重第三中学を卒業した作家横光利一が、体験を元にして少女との淡い恋物語を描いた自伝的小説です。「雪解のつどい」は毎年様々な講師を招いて横光利一とその作品を顕彰する会です。

2016年は横光利一が三重三中を卒業してから100年にあたり、今回は現役の上野高校生が会場に招かれました。当時の三中の『校友会報』をもとに横光利一の学生生活を振り返った後、本校の放送部4名(2年生の松田唯乃さん、松山友亮さん、山本絢加さん、1年生の山内萌恵さん)が『雪解』を朗読しました。また卒業生の里平健太さん、森永元希さん、1年生の冨澤有佐さんが感想を発表しました。三中生と上高生との共通点や相違点、「肉食系女子」が見た『雪解』の恋愛観など、高校生ならではの視点に会場からは笑いと感心の声があがりました。

3月17日(木)に上野高校の1年生が1グループ7人に分かれ、「百人一首大会」を行いました。生徒は1枚の札に白熱し、楽しんでいました。

結果は以下の通りです。
クラス 1位 1年7組
2位 1年5組
3位 1年3組
個人 1位 冨澤有佐さん(1年7組)
2位 森林夏強くん(1年5組)
3位 權蛇由夏さん(1年3組)
4位 菅 美帆さん(1年5組)
5位 藤本有見加さん(1年2組)
6位 幾世冬悟くん(1年7組)
7位 古川明香里さん(1年3組)
8位 大櫃温仁くん(1年7組)
8位 加藤大暉くん(1年7組)
10位 西前千都世さん(1年5組)
10位 堀川出帆くん(1年7組)


当校は、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を文部科学省よりいただいております。