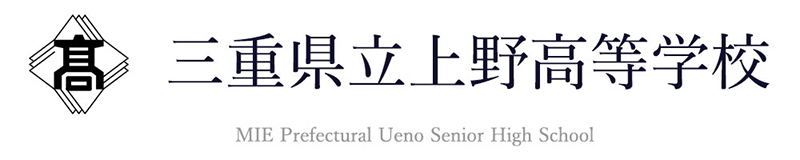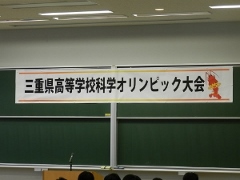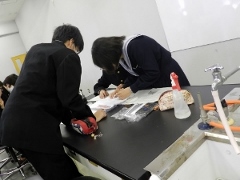厳しい暑さが残る9月に本年度の前期が再開し、途中で後期のスタートを挟んで文化祭から今月の後期中間考査まで、日々の授業だけでなく、さまざまな学校・学科行事や部活動、模擬試験などを通して、皆さんは多くのことを学び、あれこれ考えたり、迷ったり、悩んだりしたことと思います。どんなことが印象に残っていますか。何を深く考えましたか。そして、どんな出会いがありましたか。
私は、秋のある日、ある詩の中の言葉と衝撃の出会いをしました。実は今でもその詩の意味について考えを巡らすことがあります。それは、「いのちより大切なもの」という詩です。
いのちが一番大切だと
思っていたころ
生きるのが
苦しかった
いのちより
大切なものが
あると知った日
生きているのが
嬉しかった
この詩の作者は星野富弘さんという方です。知っている、聞いたことがあるという人もいると思います。星野さんは、中学校の体育の教師をしていた24歳の時、部活動の指導中に宙返りをして首から落ち、首から下の運動機能を失ってしまいます。その後、身体を動かすことができず上を向いたまま寝たきりの状態で9年間の入院生活を送ります。病室の天井を見ながら、「あれがなかったら俺の人生は違っていた」「いっそのこと生まれなければよかった」などと後悔と失意を繰り返します。そして、唯一動かすことができる口に筆をくわえて絵を描き、詩を書き添える詩画を創り始めます。筆に巻いたガーゼに血をにじませながらの創作です。やがてそれらの作品は出版され、多くの人々に感動と生きる希望を与え続けています。
さて、「いのちより大切なもの」とは一体何か。皆さんはどう考えますか。この詩が発表されてから、多くの人が星野さんに、「いのちより大切なものとは何ですか。」と尋ねます。星野さんは、このように答えていたそうです。「その答えはこうですよ、と言うことは簡単だけど、きっとそれは意味のないことです。自分で苦しみながら見つけた時に、あなたにとって意味があるのです。」と。しかし、2011年3月11日の東日本大震災以降、この質問をする人がいなくなったそうです。
いのちはかけがえのない大切なものです。いのちより大切なものなどありません。しかし、星野さんはこのように言います。「津波が迫る中、水門を閉めるために津波のほうに向かって走っていった人、人の波に逆らうようにして『津波が来るぞ』と知らせて回っていた人。その人たちは皆、自分のいのちよりも大切なものに向かっていった人ではないかと思います。」
「いのちより大切なもの」皆さんは何だと思いますか。
私は、星野さんの著作のなかに、その詩の題名がタイトルとなった『いのちより大切なもの』という絵本があることを知りました。早速、図書館の上原先生にお願いして、その絵本を所蔵している名張西高校図書室から借りていただきました。その絵本の冒頭に、「小さな花からのメッセージ」というエッセイがあります。そこに東日本大震災のことが書かれています。地震の激しい揺れに車椅子ごと倒れる恐怖に駆られ、テレビをつけると家々が津波に吞み込まれていく凄まじい光景と叫び声、映画の一場面のような映像に、「こんなことが本当にあっていいのだろうか」と瞬きを繰り返したそうです。心の奥に積み上げてきたものが、次々となぎ倒されていくように感じた星野さんは、「自分が書くものなど、あまりにもちっぽけで何の意味もないように思えて、何も手につかなくなってしまった。創作意欲の根元までさらわれてしまったような気がした。」と告白しています。
ところがある日、星野さんは被災状況を映し出すテレビを観ていて、こんな情景を目にします。瓦礫の間に、倒れそうな一本の木の折れ曲がった枝先に花が咲いていて、その木の周りに津波で肉親や家を失くしたであろう人達が、まるで希望の光を見つけたようにたたずんでいる情景です。その情景を見た時、それまで何もできないでいた星野さんは、「もう一度やってみよう。人の心に希望をもたらしてくれる花を、これからも描いていこう。」と思ったそうです。
私は、この時に星野さんは「いのちより大切なもの」を見つけたのではないかと思うのです。「使命」という言葉があります。「命」を「使う」と書きます。自分のいのちをどう使うか、その方法を星野さんは見つけた。人に希望をもたらす花の絵を描くこと、それが星野さんの見つけたいのちを使う方法なのではないか。自分の「使命」を見つけたことで、いのちへの執着を断つことができたのではないか。だからこそ、
いのちより
大切なものが
あると知った日
生きているのが
嬉しかった
という詩の一節が生まれたのだと思うのです。
「いのちより大切なもの」。それは、人のために自分に与えられたいのちを精一杯生きることだと星野富弘さんに教えてもらったように思います。
明日から始まる冬休みの前に、「この一年、自分は精一杯生きたか。」と自分に問うてみてください。以上で後期全校集会の話を終わります。
******************************************
一旦終わったうえで、最後に一言。
もしも皆さんの中に、この詩について私はこう考えるという人がいれば、その考えを是非聴かせてほしいと思います。どうぞ校長室のドアをノックしてください。私も勉強したいので。お待ちしています。これで本当に終わります。