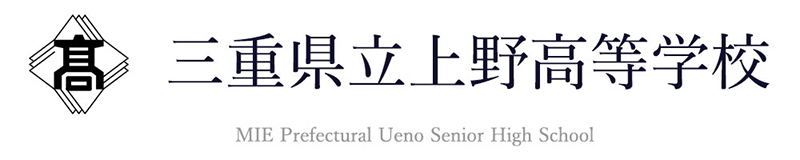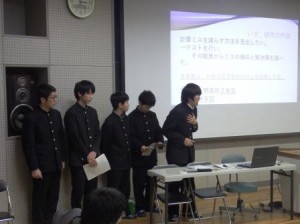新しい春の訪れを感じさせる今日の佳き日、御来賓の皆様、卒業生の保護者の皆様の御臨席のもと、平成28年度卒業式を挙行できますことは、私共のこの上ない喜びであり、誠に嬉しく存じます。本校を代表し、深く感謝申し上げます。
さて、卒業生の皆さん。皆さんの努力が実を結び、卒業の時を迎えたことに、本校職員を代表して心から祝福の言葉を述べたいと思います。「上野高校卒業、本当におめでとう。」
そして、今日まで皆さんを支えてくれた多くの人々、ことに皆さんの成長を深い愛情で見守り続けていただいた保護者の皆様に、心からの敬意と感謝の気持ちを込めて、お祝いの言葉を申し上げたいと存じます。「保護者の皆様、本日はお子様のご卒業、誠におめでとうございます。」さぞかし感慨もひとしおのものがおありであろうと拝察いたします。心からお喜びを申し上げます。
卒業生の皆さんの中には、これで学校教育を終え、職業人として本格的に実社会の中に入っていく人がいます。また、卒業後も進学して新たな学校生活を始める人もいます。どのような道を歩むにせよ、高校を卒業するということは、責任ある存在として社会に認知されるということです。今後は、責任に裏打ちされた行動が一層求められます。自己責任の重さは、今までとは比べようがないものになります。
高校卒業の時。それは、人に愛される自分から、人を愛する自分に変わる時です。甘えからきっぱりと決別し、感謝の心で一人立ちする時です。そして、学ぶべきことを与えられる自分から、何を学ぶべきかを自分で考え、自力で学ぶ自分に変わる時です。
いかなる状況にあっても、どんな人生を生きようとも、学ぶことに終わりはありません。生涯、辞書を引き続けてください。常に新しい知識を学び、知ることに終わりなきことを肝に銘じてください。
学ぶことは変わることです。進化論を説いたチャールズ・ダーウィンは、こんな言葉を私たちに残しています。「何が生き残るのか。最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるのでもない。唯一生き残るものは変化できるものである。」変わり続けるものだけが生き残るというのは、普遍の真理なのです。
ところが、昨今、「自分は変わらない」「自分を変えられない」と決め付ける若者が増えていると言われています。「生まれ持った素質によって人生は決まる。」と考え、「あれこれ考えて行動しても、結局はなるようにしかならない。」とか、「頑張って良い結果を出しても、所詮それは本物ではない。」などと思えてしまうのだそうです。生まれ持った素質こそが「自分らしさ」であり、生得的な特性が自分の「個性」である。そして、自分の「個性」に見合う仕事でなければ働く意味がない。ひいては、それが見つかるまで職には就かないなどと身構えてしまい、社会に出る敷居を高く感じてしまうわけです。
「個性」とは、他者と交わりながら何かを成し遂げていく中で、これが自分の持ち味だと気づいていくものです。自己とは、自分とは、対人関係の中で構築されるものであるが故に、大きな可塑性を持っているのです。自分は、つくり直せるのです。
生まれ持った「自分らしさ」への過剰なこだわりを捨てた時にこそ、人生も一層豊かなものになり、輝き始めるのではないか。卒業の時、新たな他者と出合い、新たな対人関係を築いていこうとする今が、その時だと言いたいのです。
さあ、卒業生の皆さん、別れのカウントダウンが始まりました。旅立ちの時です。
卒業生よ、思い出に沈殿するな。未来に向かって躍り出よ。
卒業生よ、首を垂れるな。希望の青空を仰ぎ見て、悠々と真っすぐに歩んで行け。
「大いなる明日」は、今の君達のためにこそある。
最後になりましたが、御多用の中、御臨席賜りました御来賓の皆様方、本日は誠に有難うございました。これからも本校に温かい御支援を賜り、卒業生、在校生を見守って頂きますようよろしくお願い申し上げます。
卒業生9名の門出を祝い、前途に幸多かれと祈りつつ、式辞と致します。