生徒心得

1.身だしなみについて
(頭髪・服装・化粧・装飾品など)
1)服装(制服の規定について)

着用規定(補足)
①AタイプとBタイプをまたぐ組み合わせも可とする。
②夏服期間はネクタイ・リボンを着用しなくてもよい。ネクタイ・リボンを着用しない場合にはシャツ・ブラウスの第1ボタンのみ外しても良い。
③夏服期間にネクタイ・リボンを着用する際には、シャツ・ブラウスの全てのボタンを留めること。
④夏服では上着は着用しない。
⑤襟のボタンは常に留めておくこと。
⑥シャツ・ブラウスの裾は、スラックスまたはスカートの中に常に入れること。
⑦譲り受け制服の着用も認める(旧仕様も可)。ただし、以下の点に注意すること。
スカート…着用前に必ず生徒指導室に持参して長さを測定する必要がある。適切な長さのスカートのみ着用を認める。修理が必要な場合は、生徒指導室で許可証を受け取り、業者に依頼すること。
夏用のスラックス(紺)またはスカート(紺)…夏服期間のみ着用することができる。
シャツ・ブラウス…冬服のシャツ・ブラウスについては冬服期間に、開襟シャツ・ブラウスについては夏服期間に着用できる。
⑧上着・スラックス・スカート・セーター等には必ず名前を書いておくこと。
大きな違いはボタンの付け方が反対になっていることである。その他、少しではあるが、形の違いがある。
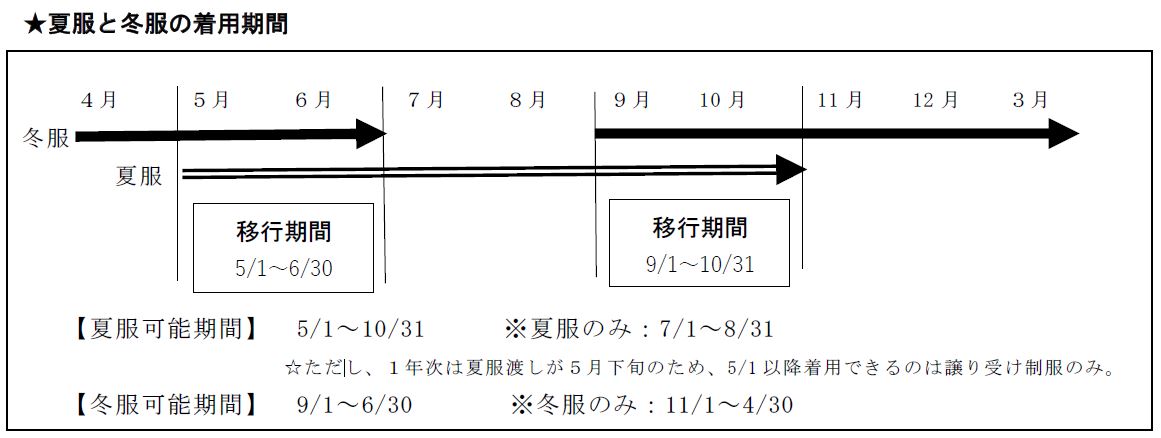
2)リボン、ネクタイ
上着を着ている時は、どちらかを必ず着用する。忘れた場合は生徒指導室で借りる。
3)防寒着
今年度(2024年度)は、防寒着について、以下のように定める。
(ア)上着は特に指定しないが、通学にふさわしいものとする。
(イ)防寒着としてのズボンは、体育時のジャージ、または学校指定のウインドブレーカーのみ許可する。ただし、これらを着用する際、スカートの下に履くことは禁止する。
部活動の早朝練習の登校時と部活動後の下校時は、クラブ指定のジャージまたはウインドブレーカーを着用することを認める。ただしこれらの場合、クラブの早朝練習が終わったら、必ず制服、または体育時のジャージか学校指定のウインドブレーカーに着替えなければならない。
(ウ)制服のブレザー、ズボン、スカートは必ず持参して、いつでも正しい服装ができるようにしておく。
式典や集会時、また大職員室、チューター室、進路指導部、生徒指導部、体育教官室、保健室、司書室その他、先生の居所に入室する際は、制服を正しく着用する。
※防寒着着用可能期間は11月から翌年3月までとする。その他、指示がある場合には着用できる期間を別途定める。
※上記規定は令和6年度限定の規定とし、新たな規定については来年度の防寒着着用期間までに、協議のうえ提示する。
4)ひざ掛け
授業や集会等で教室や体育館等でのひざ掛けの使用を認める。なお、防寒着をひざ掛け替わりに使用することもできる。ただし、定期考査や実力テストにおいては、ひざ掛けを使用することができない。また、廊下等でひざ掛けを巻いて歩くことはできない。
5)登下校時の服装について
平常授業時の登下校は原則、制服を着用する。ただし、特別な日(体育祭・クラスマッチなど)や雨天時の合羽の下に着用する場合は学校指定ジャージ(体操服)での登下校を認める。
また、部活動の朝の練習前の登校、放課後の練習後の下校については、学校指定ジャージ(体操服)およびクラブ指定ジャージの着用を認める。
6)靴
安全に通学できるものとする。
7)頭髪など
脱色・染色・パーマ類・変形刈り・整髪料などによる著しい加工は施さない。また、アイロンやドライヤー等により髪がひどく変色しないように気をつける。かつら等の使用については、特別な理由がある場合のみ認める。眉毛・まつ毛の著しい変形を施さない。
8)装飾品など
シュシュ、リボン等については、華美なものは避け、装飾品は禁止とする。
ピアス・ネックレス・指輪・ブレスレット・カラーコンタクトなどを付けてはならない。
9)化粧品類など
マニキュア、化粧・口紅・色付きリップなどを施ほどこさない。
10)その他
・やむを得ない事情により異装せざるを得ない場合は、異装許可願(黄色用紙)を生徒指導部に提出し、許可を受ける。
・宿泊を伴う公式大会(東海大会や全国大会等)について、授業途中に学校から出発する場合は、授業もクラブジャージで受けることを認める。また、この場合クラブジャージでの登下校も認める。
・配慮の必要な生徒は、生徒指導部に相談すること。
2.法・ルールの遵守、手続き等について
1)『生徒心得(校則)』・公共マナー・社会道徳・社会規範・法律等を遵守する。
2)パチンコ店など法律上18歳未満の入店・入場が禁止されている店舗や施設等については、たとえ18 歳に達したとしても本校在学中は入店・入場・アルバイト等をすることを認めない。
3)校舎・校具を大切にする。
4)遅刻・早退・外出に関しては、所定の手続きを各学年でとる。
①遅刻(朝の遅刻・授業遅刻)
遅刻生徒は各学年職員室で遅刻連絡カード(白用紙)の手続きをする。
授業遅刻の場合は、教科担任に遅刻連絡カードを渡してから授業を受ける。
②早退
早退生徒は各学年職員室でチューターの許可、または、保健室の許可(保健室からチューターに連絡)をうけ、早退許可証(青用紙)の手続きにより下校する。
早退生徒は帰宅しだい、学年室に連絡する。
③外出
外出生徒は生徒指導部、学年及びチューターの許可を得て、外出許可証(ピンク用紙)の手続きにより外出する。外出終了後、外出許可証を返却する。
④欠席
原則、欠席する当日朝に保護者が学校に連絡する。
5)原則、4)の手続きを取らず、授業あるいは学校(行事も含む)を遅刻・早退・欠席してはならない。
6)テスト(定期考査・実力テスト・宿題テスト・小テスト)・課題の不正行為(改ざんも含む)をしてはならない。
テスト・課題の不正行為(改ざんも含む)が発覚した場合、指導の対象とする。テストの不正行為については、当該科目を0点とする。定期考査・実力テスト・宿題テストの規則については、各教室に掲示される『考査時の生徒心得』を参照すること。
3.交通安全等について
1)交通法規・マナーを遵守すること。道路に広がって通学しない。
2)自転車通学者は、二人乗り、並進、無灯火、傘さし運転、イヤホン等耳をふさぐようなものを着用しての運転、携帯電話を操作しながらの運転等はしてはならない。
☆学校まで自転車で通学する生徒は自転車通学許可届を提出し、許可された生徒は自転車点検を受け、所定のステッカーを自転車に貼ること。また、必ず施錠(二重ロック)すること。
3)自動車での送迎は、原則8:15~8:50と放課後30分間は野球場前駐車場を使用する。
4)原付きバイク、自動二輪車、四輪自動車は、原則運転してはならない。
5)特定小型原動機付自転車いわゆる電動キックボードを使用した通学を禁止する。
6)自動車学校には許可なく入校してはならない。自動車学校への入校・通学については、『自動車学校通学に関する生徒指導心得』および3年次に配付される『自動車学校への入校について』等を参照すること。
7)交通事故を起こした場合、交通事故の被害を受けた場合、および交通違反で指導された場合は、すみやかにチューターまたは生徒指導部に届け出ること。
4.免許の取得について
在学中は、二輪車・四輪自動車等の運転免許取得を原則として禁止する。ただし、以下のア・イの場合に限り、認める場合がある。
ア 3年次生徒で、以下の①~③に該当すると認められた場合。
①就職(警察官、郵政等)に関連し、二輪免許または普通自動車免許を取得しなければならない場合。
②3月以降運転免許試験を受けに行く時間的余裕がない場合(進学先での練習など)。
③その他特別な事情がある場合。
*運転免許取得希望者は、「在学中の運転免許取得特別許可願い」を提出し、必要があれば練習計画表の写し等も一緒に提出する。
*原則、運転免許取得後、卒業までは運転できない。
イ 次の①または②の条件に該当すると認められた場合の原動機付自転車(原付)(50cc 以下)の免許取得。
①鉄道、バスなどの交通機関及び自転車の利用が不可能な地域からの通学などで、校長が特にやむを得ない事情があると認める場合。
②その他校長が特に必要と認める場合。
【イの場合(原付の運転免許取得)の規定及び運転について】
1)原付による学校までの通学は、原則として禁止する。ただし、鉄道、バスなどの交通機関及び自転車の利用が不可能な地域からの通学に限り、審議のうえ、最寄りの駅までの通学を許可する。特別の事情のある場合は、そのつど審議して許可する。
2)原付運転免許取得希望者は、「原付運転免許取得許可願い」を生徒指導部に提出すること。
3)原付運転免許取得を許可された者は、「原付運転誓約書」および「原付運転調査書」を提出すること。また、校長が発行する「原付運転免許受検許可書」の交付を受けること。
4)原付運転免許を取得した場合、直ちに学校に届け出ること。その際、ステッカーの交付を受け、通学に使用する原付に貼付すること。
5) 原付による通学を許可された者は、関係機関等が実施する安全運転講習会を免許取得時および年度毎に1回以上受講しなければならない。
6)原付による通学を許可された者は、交通法規を遵守すること。
7)原付による通学を許可された者が、交通法規に違反した場合、または人身事故をおこした場合は許可を停止し、もしくは取消すことがある。また、校則、法規、マナー・ルール等に違反した場合も許可を停止、もしくは取消すことがある。
5.その他
1)所持品には名前を明記し、ロッカーを使用する。ロッカーは施錠する。
2)遺失物、拾得物は直ちにチューターまたは生徒指導部に届けること。
3)携帯電話については、授業中は電源を切りかばんに入れること。考査時は電源を切り、教室内には持ち込まないこと。また、廊下等での歩きながらの使用は慎むこと。行事等においては使用を禁止する場合もある。
4)アルバイトは届け出または許可を受けた場合に行うことができる。ただし、以下の項目を守ること。
(1)土・日・祝日・長期休業中(春・夏・冬休み)は届け出により行うことができる。長期休業中は平日も行うことができる。1年次に関しては、夏休み以降に行うことを原則とする。
(2)平日(3年次の家庭学習期間も含む)のアルバイトについては、以下の【条件】①・②を満たしている、学校生活(成績、出席)が良好な生徒にのみ許可する。また、必ず保護者の了解を必要とする。1年次に関しては、夏休み以降に行うことを原則とする。希望する生徒は、生徒指導室まで申し出ること。
直近の定期考査の赤点が1つまで(赤点とは30点未満のことをいう。ただし、平均点が50点未満の場合は、平均点の半分未満を赤点とする。)
【条件】②
前の学期(前期または後期)および現在の学期の二期とも欠席・遅刻・早退の合計が10日(10回)以内(公欠、出席停止を除く)
※1年次の前期についてはこの学期のみで判断する。
※平日アルバイトを始めた後、条件を満たしていない状況になった時点で、平日アルバイトはできないものとする。
(3)考査発表日から考査最終日までは禁止する。
(4)1日8時間以内とする。
(5)午後8時までとする。
(6)飲酒を伴う接客業は禁止する。
(7)原則、成績不振者は行うことができない。
【土・日・祝日・長期休業中のアルバイトを禁止する条件】
対象となる素点、評点について赤点が3つ以上となった場合。
〔土・日・祝日・長期休業中のアルバイトに関する「赤点」とは〕
対象となる定期考査の素点、前期評点、学年評点について30点未満のことをいう。
ただし、平均点が50点未満の場合は、平均点の半分未満を赤点とする。
【対象と禁止期間】
| 月 | 対象となる素点、評点(時期) | 禁止期間(学習重点期間) |
|---|---|---|
| 7月 | 1・2年次前期中間①②素点平均 3年次仮評点 |
前期期末まで |
| 10月 | 前期評点 | 後期中間まで |
| 12月 | 後期中間素点 | 後期期末まで |
| 3月 | 学年評点(3年次は2月) | 前期中間①まで(3年次は卒業まで) |
※アルバイト届は年度ごとに行う。
※雇用主(店長等)に「本校生徒のアルバイトの規定について」を必ず渡さなければならない。
5)校内に以下のような不要な物を持ち込んで使用しないこと。
携帯電話の充電器、ドライヤーや頭髪用アイロン、ゲーム機など
諸届ルート
| 遅刻 | 各学年職員室で用紙(遅刻連絡カード)に記入する → 教室で教科担任に渡す |
|---|---|
| 早退 | チューターより早退許可証を受け取る → 帰宅後すぐ、学年へ連絡する 保健室で早退許可証を受け取る → チューターまたは学年 → 帰宅後すぐ、学年へ連絡する |
| 外出 | チューター・学年より外出許可証を受け取る → 学校に戻ったら、チューターに連絡する |
| 異装 | 生徒指導室で異装許可証を受け取る |
| アルバイト | アルバイト届用紙 生指 → 必要事項記入 → チューター → クラブ顧問 → 生指 |
| 自転車通学 | 自転車通学許可届用紙(生指) → 必要事項記入 → 生指(ステッカー代200円必要) |
| 正門での送迎利用証 | 生徒指導室で手続き → 「登下校混雑時 正門での送迎利用証」を発行 → 期間後生指へ返却 |
| 盗難・被害・事故 | 生徒指導室(被害届・紛失届・事故報告書用紙) |
| 学割 | 学生生徒旅客運賃割引証交付願用紙(事務室) → 必要事項記入 → チューター → 生指 → 事務室 |
| 通学証明書(再発行) | 通学証明書再発行用紙(事務室) → 必要事項記入 → チューター → 事務室 |
| 学生証(再発行) | 学生証再発行用紙 事務室 → 必要事項記入 → チューター → 事務室 |
