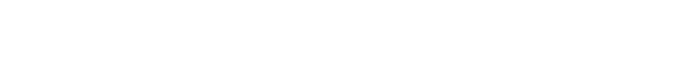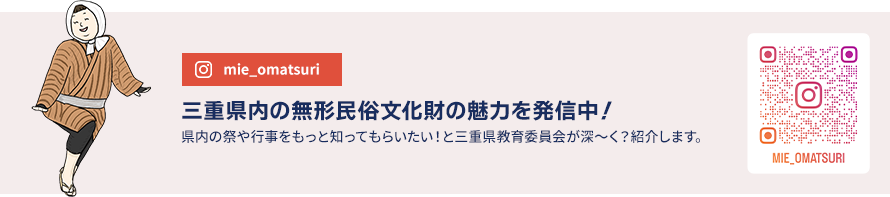2004年9月28日
切原富士講
市町指定・市町選択

指定区分
市町指定・市町選択
季節区分
夏(6~8月)
地域区分
南勢志摩
開催地
南伊勢町
祭りの種類
その他
みえ祭り協力隊
-動画
-
【開催日】7月第1日曜日
【開催地】南伊勢町切原浅間山 切原コミュニティーセンター
南伊勢町切原で、7月第1日曜日に行われている。講員が垢離を行い、餅を搗いたのち、浅間山に奉幣する。
午前1時ごろから、昨年の当屋を務めた精進人が、釜の火を焚きつけ、もち米を蒸籠で蒸す。蒸しあがったら臼に移し、精進人4人が竪杵を持ち、1人が手返し水をとって、浅間道中歌や餅つき唄に合わせて、餅を搗く。小搗き、練り搗き、本搗きの手順がある。
搗きあがった餅は、丸餅にされて志納者などに配られたり、桶に入れられ祭壇に供えられ、大祭終了後に、講中の家々に配分されたりする。
夕垢離の後、登頂行列が行われる。男たちは道中歌を歌いながら、竹で作られた、紙垂という白い紙の垂れ飾りがつけられた「大幣」二本と「小幣」二本幣を担いで、浅間山を登る。
二本の小幣山の中腹に立てたのち、履物を脱いでから二本の大幣を山頂まで運ぶ。山頂では大幣を立て、祠に祈祷、経典や真言を唱えて浅間神を浅間山に迎え、豊穣や村内の平安を祈り、最後に神社の周りを3回まわり礼拝する。
「講」で行事が維持されていること、竪杵を用いた4人が連携して行う餅の搗き方が特徴的である。
【開催地】南伊勢町切原浅間山 切原コミュニティーセンター
南伊勢町切原で、7月第1日曜日に行われている。講員が垢離を行い、餅を搗いたのち、浅間山に奉幣する。
午前1時ごろから、昨年の当屋を務めた精進人が、釜の火を焚きつけ、もち米を蒸籠で蒸す。蒸しあがったら臼に移し、精進人4人が竪杵を持ち、1人が手返し水をとって、浅間道中歌や餅つき唄に合わせて、餅を搗く。小搗き、練り搗き、本搗きの手順がある。
搗きあがった餅は、丸餅にされて志納者などに配られたり、桶に入れられ祭壇に供えられ、大祭終了後に、講中の家々に配分されたりする。
夕垢離の後、登頂行列が行われる。男たちは道中歌を歌いながら、竹で作られた、紙垂という白い紙の垂れ飾りがつけられた「大幣」二本と「小幣」二本幣を担いで、浅間山を登る。
二本の小幣山の中腹に立てたのち、履物を脱いでから二本の大幣を山頂まで運ぶ。山頂では大幣を立て、祠に祈祷、経典や真言を唱えて浅間神を浅間山に迎え、豊穣や村内の平安を祈り、最後に神社の周りを3回まわり礼拝する。
「講」で行事が維持されていること、竪杵を用いた4人が連携して行う餅の搗き方が特徴的である。