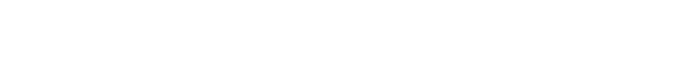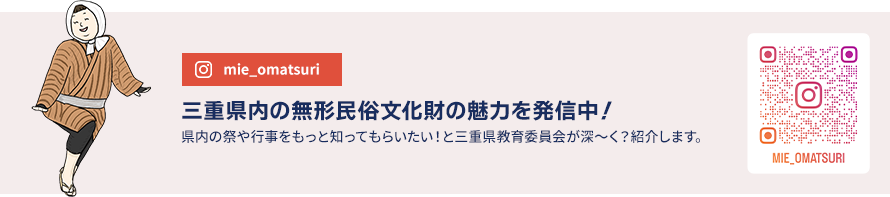2009年3月11日
陽夫多神社祗園祭の願之山行事
県指定・県選択

指定区分
県指定・県選択
季節区分
夏(6~8月)
地域区分
伊賀
開催地
伊賀市
祭りの種類
風流踊り
みえ祭り協力隊
-動画
-
【開催日】8月1日
【開催地】伊賀市
願之山行事は、毎年8月1日に伊賀市馬場の陽夫多神社祇園祭に行われる行事で、小踊りと大踊りの2種類の踊りが踊られる。
願之山は大太鼓3丁を載せた4輪の台車に6本のハタを立てた曳山で、30人ほどで境内を曳きまわされる。小踊りは持ち手と打ち手に分かれた6組12人の幼児が親の介添えで小太鼓を打ちつつ横に行っては戻るだけの単純な踊りである。大踊りは願之山を囃す踊りで、6人の青年が主宰者の音頭とともに曳山に載せた大太鼓を打ち進む。
願之山の曳行は3度に分けて行われ、1度めの曳行を「互礼」(ごれい)と呼び、2度めの曳行後、再び小踊りとなる。3度めの曳行後は、願之山が拝殿前に曳き据えられて「七遍返し」が行われる。七遍返しは大太鼓を打ち囃す大踊りの周りを小踊りの一団が左まわりに7回まわるというもので、これをもって願之山行事のすべてが終了する。
行事は主宰者のリードで進行し、「さんよ-りさんよーり げにもさ-に」の囃し詞が付く特異なもので、中世後期に流布した拍子物(はやしもの)の特色を良く残す。拍子物とは踊りそのものが囃しの機能を帯びる集団の踊りであり、疫神を囃して鎮め送るのがその本質である。また、願之山行事に先立って行われる花揚げは、氏子8地区から奉献される花傘の造花や団扇を参拝者が奪い合うもので、花傘に疫神をよらせて鎮め送り、災厄を免れようとする行事である。
願之山行事は、「願(がん)ほどきの踊り」とされ、掛けられた願の数だけ繰り返し踊るものであり、疫神を祀る京都祇園祭の山鉾行事の本質を如実に物語る学術的価値の高い貴重な行事である。
【開催地】伊賀市
願之山行事は、毎年8月1日に伊賀市馬場の陽夫多神社祇園祭に行われる行事で、小踊りと大踊りの2種類の踊りが踊られる。
願之山は大太鼓3丁を載せた4輪の台車に6本のハタを立てた曳山で、30人ほどで境内を曳きまわされる。小踊りは持ち手と打ち手に分かれた6組12人の幼児が親の介添えで小太鼓を打ちつつ横に行っては戻るだけの単純な踊りである。大踊りは願之山を囃す踊りで、6人の青年が主宰者の音頭とともに曳山に載せた大太鼓を打ち進む。
願之山の曳行は3度に分けて行われ、1度めの曳行を「互礼」(ごれい)と呼び、2度めの曳行後、再び小踊りとなる。3度めの曳行後は、願之山が拝殿前に曳き据えられて「七遍返し」が行われる。七遍返しは大太鼓を打ち囃す大踊りの周りを小踊りの一団が左まわりに7回まわるというもので、これをもって願之山行事のすべてが終了する。
行事は主宰者のリードで進行し、「さんよ-りさんよーり げにもさ-に」の囃し詞が付く特異なもので、中世後期に流布した拍子物(はやしもの)の特色を良く残す。拍子物とは踊りそのものが囃しの機能を帯びる集団の踊りであり、疫神を囃して鎮め送るのがその本質である。また、願之山行事に先立って行われる花揚げは、氏子8地区から奉献される花傘の造花や団扇を参拝者が奪い合うもので、花傘に疫神をよらせて鎮め送り、災厄を免れようとする行事である。
願之山行事は、「願(がん)ほどきの踊り」とされ、掛けられた願の数だけ繰り返し踊るものであり、疫神を祀る京都祇園祭の山鉾行事の本質を如実に物語る学術的価値の高い貴重な行事である。