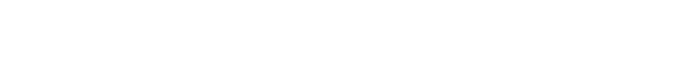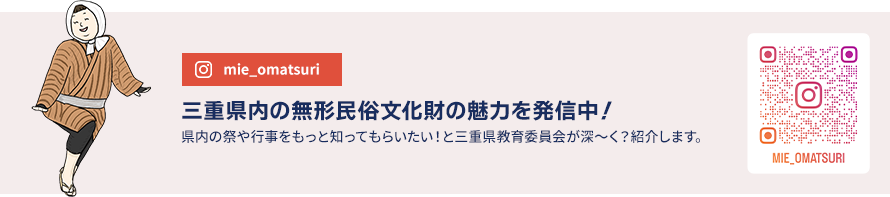2019年1月28日
比自岐神社の祇園踊
県指定・県選択

指定区分
県指定・県選択
季節区分
夏(6~8月)
地域区分
伊賀
開催地
伊賀市
祭りの種類
風流踊り
みえ祭り協力隊
-動画
-
【開催日】7月第4日曜日
【開催地】伊賀市比自岐
毎年7月第4日曜、比自岐神社(伊賀市比自岐)の祇園祭に奉納されている踊りで、県内で「かんこ踊り」と総称される、風流太鼓踊りの派生形である。地元には万延元(1860)年の歌本複写が残されており、雨乞い祈願に太鼓踊りが踊られてきたことが知られる。踊りは大太鼓と貝の拍子が中心で、鞨鼓を打つ踊り手は登場しない。大太鼓を打つ時の踊り子の所作が「踊り」に発展したものである。大太鼓を数人が一節ずつ交代して打つ芸態は、旧伊賀町や旧阿山町のかんこ踊りとは異なっている。類例は伊賀市法花(廃絶)、同島ヶ原(歌と拍子のみ伝承)、奈良県奈良市都祁(つげ)吐山(はやま)、宇陀市室生大野の太鼓踊りなど、伊賀西部から奈良県東部に分布している。
現在伝承されている曲目は、「鐘巻(かねまき)踊」「陣立(じんたち)踊」「こじんやく踊」「よめご踊」「かたびら踊」の5曲である。
基本的な踊りの体形は、神殿・鳥居を背に歌出しが並び、向い合わせに大太鼓を2台並べる。大太鼓1台につき踊り子が6人付き、交代で太鼓を打つ。貝吹きは太鼓の左後方に3名控える。神社境内の四方には、くじ付きの団扇を結びつけた笹竹や、枝垂れ桜に似せた造花「ほうろ花」が立てられる。「ほうろ花」は、伊賀地域のかんこ踊りや祇園祭に特徴的なものである。衣装は、踊り子が丈の短い浴衣に黄色の帯と襷、頭には花笠を被り、足は素足である。歌出しは菅笠を被り、浴衣に黒の羽織を着て、団扇を持つ。貝吹きは浴衣である。
伊賀のかんこ踊りの大きな特徴は、「じんやくや」「じゅんやくや」などと節毎に囃す「じんやく(順逆)踊り」を伝えるところにある。じんやく踊りは伊賀地域を中心にして近江・山城・大和・伊勢など周辺地域に分布しており、17世紀以降、新大仏寺(伊賀市富永)の雨乞い信仰とともに、周辺に伝播したと推測されている。このじんやく踊りは、「神役」「重役」などと記す例が語るように特別な曲とされるが、節拍子が句毎に変化する難しい曲でもあり、肉体的負担が大きいため、廃曲となった例が多い。じんやく踊りの継承は、芸能の発生や成立を示しており、学術的な価値が高い。また、比自岐神社の祇園踊は、伊賀西部から奈良県東部の風流太鼓踊りの地域的特色をよく伝えるものとして、旧伊賀町や旧阿山町のかんこ踊りと並んで重要である。
【開催地】伊賀市比自岐
毎年7月第4日曜、比自岐神社(伊賀市比自岐)の祇園祭に奉納されている踊りで、県内で「かんこ踊り」と総称される、風流太鼓踊りの派生形である。地元には万延元(1860)年の歌本複写が残されており、雨乞い祈願に太鼓踊りが踊られてきたことが知られる。踊りは大太鼓と貝の拍子が中心で、鞨鼓を打つ踊り手は登場しない。大太鼓を打つ時の踊り子の所作が「踊り」に発展したものである。大太鼓を数人が一節ずつ交代して打つ芸態は、旧伊賀町や旧阿山町のかんこ踊りとは異なっている。類例は伊賀市法花(廃絶)、同島ヶ原(歌と拍子のみ伝承)、奈良県奈良市都祁(つげ)吐山(はやま)、宇陀市室生大野の太鼓踊りなど、伊賀西部から奈良県東部に分布している。
現在伝承されている曲目は、「鐘巻(かねまき)踊」「陣立(じんたち)踊」「こじんやく踊」「よめご踊」「かたびら踊」の5曲である。
基本的な踊りの体形は、神殿・鳥居を背に歌出しが並び、向い合わせに大太鼓を2台並べる。大太鼓1台につき踊り子が6人付き、交代で太鼓を打つ。貝吹きは太鼓の左後方に3名控える。神社境内の四方には、くじ付きの団扇を結びつけた笹竹や、枝垂れ桜に似せた造花「ほうろ花」が立てられる。「ほうろ花」は、伊賀地域のかんこ踊りや祇園祭に特徴的なものである。衣装は、踊り子が丈の短い浴衣に黄色の帯と襷、頭には花笠を被り、足は素足である。歌出しは菅笠を被り、浴衣に黒の羽織を着て、団扇を持つ。貝吹きは浴衣である。
伊賀のかんこ踊りの大きな特徴は、「じんやくや」「じゅんやくや」などと節毎に囃す「じんやく(順逆)踊り」を伝えるところにある。じんやく踊りは伊賀地域を中心にして近江・山城・大和・伊勢など周辺地域に分布しており、17世紀以降、新大仏寺(伊賀市富永)の雨乞い信仰とともに、周辺に伝播したと推測されている。このじんやく踊りは、「神役」「重役」などと記す例が語るように特別な曲とされるが、節拍子が句毎に変化する難しい曲でもあり、肉体的負担が大きいため、廃曲となった例が多い。じんやく踊りの継承は、芸能の発生や成立を示しており、学術的な価値が高い。また、比自岐神社の祇園踊は、伊賀西部から奈良県東部の風流太鼓踊りの地域的特色をよく伝えるものとして、旧伊賀町や旧阿山町のかんこ踊りと並んで重要である。