2019年1月28日
日置神社の神事踊
県指定・県選択

指定区分
県指定・県選択
季節区分
春(3~5月)
地域区分
伊賀
開催地
伊賀市
祭りの種類
風流踊り
みえ祭り協力隊
-動画
-
【開催日】4月10日
【開催地】伊賀市下柘植
毎年4月10日、日置神社(伊賀市下柘植)の春祭に奉納されている踊りで、県内で「かんこ踊り」と総称される風流太鼓踊りのひとつである。踊りの始まりは定かでないが、下柘植には嘉永元(1848)年の歌本が残る。明治41(1908)年に、愛田と下柘植の両地区にあった日置神社が下柘植の日置神社に合祀されるまでは、それぞれの地区がそれぞれの神社で祇園祭に奉納していた。戦中・戦後に幾度か中断したが、下柘植が昭和52(1977)年、愛田が昭和53(1978)年に復興してからは、下柘植2年、愛田1年の3年周期で奉納されている。
基本的な踊りの体形は、神殿・鳥居を背に貝吹きと歌4人が並び、鬼と踊り子6人は2列縦隊となる。衣装は両地区で細部は異なるが、大きくは共通している。踊り子は上衣が紺の短着物に角帯を締め、下衣は裁着袴、手先は白手甲、両足は白足袋に草履を履く。背にオチズイと呼ばれる花飾りを負い、胸前に締め太鼓を付ける。オチズイは、細く割った竹に紙を染めた花と葉をつけて枝垂れ桜に似せた背負い飾りで、伊賀及び周辺地域のかんこ踊り、祇園祭に特徴的なものである。鬼は赤鬼と黒(青)鬼がおり、腰から瓢箪やでんでん太鼓、印籠やたばこ入れをつるし、頭にシャグマ(毛髪)を被り鬼面をつける。貝吹きと歌出しは紺または白の着物に角帯を締め、半纏を羽織り、笠を被り、白手甲、白足袋、草履または下駄履きである。
【開催地】伊賀市下柘植
毎年4月10日、日置神社(伊賀市下柘植)の春祭に奉納されている踊りで、県内で「かんこ踊り」と総称される風流太鼓踊りのひとつである。踊りの始まりは定かでないが、下柘植には嘉永元(1848)年の歌本が残る。明治41(1908)年に、愛田と下柘植の両地区にあった日置神社が下柘植の日置神社に合祀されるまでは、それぞれの地区がそれぞれの神社で祇園祭に奉納していた。戦中・戦後に幾度か中断したが、下柘植が昭和52(1977)年、愛田が昭和53(1978)年に復興してからは、下柘植2年、愛田1年の3年周期で奉納されている。
基本的な踊りの体形は、神殿・鳥居を背に貝吹きと歌4人が並び、鬼と踊り子6人は2列縦隊となる。衣装は両地区で細部は異なるが、大きくは共通している。踊り子は上衣が紺の短着物に角帯を締め、下衣は裁着袴、手先は白手甲、両足は白足袋に草履を履く。背にオチズイと呼ばれる花飾りを負い、胸前に締め太鼓を付ける。オチズイは、細く割った竹に紙を染めた花と葉をつけて枝垂れ桜に似せた背負い飾りで、伊賀及び周辺地域のかんこ踊り、祇園祭に特徴的なものである。鬼は赤鬼と黒(青)鬼がおり、腰から瓢箪やでんでん太鼓、印籠やたばこ入れをつるし、頭にシャグマ(毛髪)を被り鬼面をつける。貝吹きと歌出しは紺または白の着物に角帯を締め、半纏を羽織り、笠を被り、白手甲、白足袋、草履または下駄履きである。
みんなの投稿

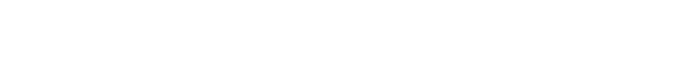
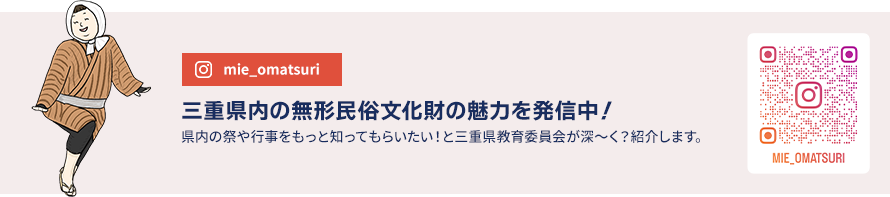
2020.4.10 撮影: Rさん