化学反応式の書き方の補足
化学式の表し方は教科書p27学習書p23に、化学反応式のつくりかたは教科書p28学習書p24〜25にあるが、さらに補足する。
元素記号
アルファベットで大文字一文字のものと、大文字と小文字の二文字で表すものがある。
ちなみに、一文字の元素記号は14種。(H,B,C,N,O,F,P,S,K,I,U,V,W,Y)
化学式
元素記号につける数字は場所によってちゃんと意味がある。それを考えずに勝手な場所に書いてあったら×だ。

■元素記号の右下に書く数字は、分子式を書くときにその元素が何個含まれているか表す。組成式のときはその元素がどんな割合で含まれているか表す。その数が1のときは省略される。
■元素記号の右上に書く数字は、イオン式でそのイオンの価数と符号(+か−)を書く。価数が1のときは省略される。(例:Cl−,Mg2+)
■元素記号の左上に書く数字は質量数を表す。質量数が取りざたされない限り書かれることはめったにない。(例:炭素14(14C)は年代測定に用いられている)
■元素記号の左下に書く数字は原子番号を表す。元素の種類によって決まっている。しかし元素は元素記号のみで識別可能なので、この数字が書かれることはほとんどない。その原子中の陽子の数や電子の数を思い出させるのには便利である。(例:11Na,17Cl)
例:水の分子式:H2O
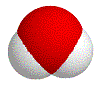
水素原子2個と酸素原子1個より構成されるので、水素の元素記号Hの右下に2という数字が付いて、酸素は1個なので酸素の元素記号Oの右下の数字は省略されている。
ついでながら、酸素分子は酸素原子2個でできているので、O2。水素分子は水素原子2個からできているのでH2。
化学反応式
化学反応式を作るときの原則は次のとおり
- 反応する物質(反応物)を左辺に反応の結果できる物質(生成物)を右辺に化学式で書き、矢印(→)で結ぶ。
- 両辺の各原子の数が等しくなるようにする。そのために分子の数を係数として表して調節する。
- 係数は最も簡単な整数比になるようにし、1の場合は省略する。
教科書のp28に酸素と水素から水が生成する反応の化学反応式をつくる例があるが、さらに詳しく解説する。
酸素 + 水素 → 水
ここに出てくる「酸素」や「水素」は自然界にある状態での物質、すなわち「酸素分子」「水素分子」である。さて、この反応を分子模型を使って表すと次のようになる。
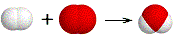
ここで両辺の原子の数を比較しよう。左辺では水素原子は2個、酸素原子は2個である。ところが、右辺では水素原子は2個だが酸素原子は1個である。反応が起こると酸素原子が消えてなくなるということはない。もうひとつの酸素原子も水素と反応して水分子を生成するものとする。そこで、両辺で酸素原子の数を合わせるために右辺で水分子を2個とすると
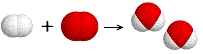
こうなると、今度は水素原子の数が右辺で4個となり、左辺の2個と合わなくなります。この反応のためには最初の段階でもうひとつ水素分子が必要となります。そこで左辺で水素分子を2個にして
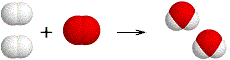
こうすると、両辺で水素原子・酸素原子の数がそれぞれ等しくなります。
化学反応式は原則1にあるように物質は化学式で表します。
2H2+O2→2H2O
ここで、H2やH2Oの前の2という数字が係数で、O2の前につけるべき係数は1なので省略されている。この化学反応式の意味していることは「水素分子と酸素分子は2:1の割合で反応し、その結果できる水分子との割合は2である」ということである。実際に水素と酸素は2:1の割合で反応する。
イオンの化学反応式
普通の化学反応式は両辺の各原子の数をそろえなければならないが、イオン反応式ではそれだけでなく電子の数も両辺でそろっていなければならない。電子の数を考えるといっても、「塩素原子(Cl)の電子数は 17個で塩化物イオン(Cl−)の電子数は
17個で塩化物イオン(Cl−)の電子数は 18個で…」などといった考え方ではかなり時間がかかる。
18個で…」などといった考え方ではかなり時間がかかる。
「Cl−はClより電子が1個多い」
「カルシウムイオン(Ca2+)はカルシウム原子(Ca)より電子が2個少ない」
といったように差で考える。そして、さらに考え方が進んで
「Cl−は1価の陰イオンだ」
「Ca2+は2価の陽イオンだ」
ということと意味していることがそれぞれ同じであると感じるようになれば、イオン反応式を考えやすくなる。(つづく)
おまけ
Coはコバルトの元素記号
COは一酸化炭素の分子式
大文字・小文字にはくれぐれも注意しましょう。
戻る

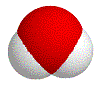
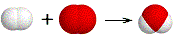
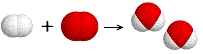
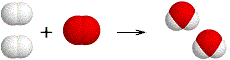
 17個で塩化物イオン(Cl−)の電子数は
17個で塩化物イオン(Cl−)の電子数は 18個で…」などといった考え方ではかなり時間がかかる。
18個で…」などといった考え方ではかなり時間がかかる。