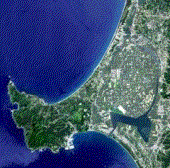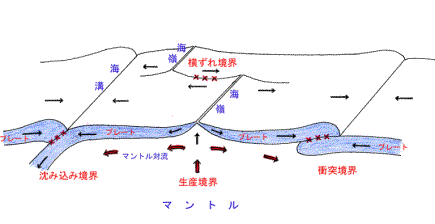理科総合B レポート No.3
1.の a
世界の最高峰・・・海抜 8,848m
最深部・・・水深10,920m
計 19,768m ≒ 20,000m
地球の半径 約6,400km = 6,400,000m
何%に当たるか計算しましょう。
2.問1 断層の種類・・・教科書P.60の 図14の解説
断層は大きく「正断層」「逆断層」「横ずれ断層」の3種類に分けられます。
正断層
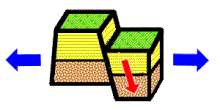
大地に両方から引っぱられる力が加わり、右側が下がったもの。
(上盤がずり落ちた場合)
逆断層
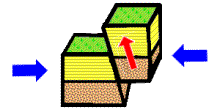
大地に両方から押される力が加わり、右側が押し上がったもの。
(上盤がはい上がった場合)
横ずれ断層
横向きの力が加わりずれたもの
単斜構造の地層・・・ 地層が単に一方向に傾いている構造の場合
問5,問6
プレートテクトニクスとは大まかに言うと、リソスフェアと呼ばれる硬い部分(プレート)が、プレートの下にある流動性に富むアセノスフェアの上をマントル対流の力によってプレートが動くという理論のことです。
マントル上部の深さ約70~250km付近に地震波速度が減少する低速度層があり,アセノスフェアとよばれます。地震波速度がおそいのは,この層内の温度が高く,物質の一部がとけてやわらかくなっているためと考えられている。
3.の【語群】の説明
モレーン(堆石)・・・・氷河地形で、氷河の侵食・運搬作用によって、末端や側方 に堆積した砂礫による地形。ヨーロッパや日高山脈でみられる。
モレーンレイク(カナダ) 日高山脈のモレーン
カルスト・・・溶けて出来る山はカルスト地形と呼ばれます。秋吉台は日本の代表的カルスト地形です。カルスト地形の自然要素は、ドリーネと呼ばれる窪地と、林立する石灰岩の岩、地下に広がる大洞窟です。
秋芳台(山口県) 神島(三重県)
カルスト地形
4.の地形
砂州・・・砂州(さす)は、湾の入り口(湾口)にできた 砂嘴が発達し、対岸またはその付近までに至った地形。 沿岸流により運ばれた砂や礫が堆積してつくられる。
 天橋立(京都):砂州
天橋立(京都):砂州
砂嘴・・・砂嘴(さし)とは、沿岸流により運ばれた砂が堆積してできる、嘴(くちばし)形の地形。砂嘴が発達する

ことで対岸またはその付近までに至ると、砂州と呼ばれる。
野付半島(北海道)
ランドサット衛星写真 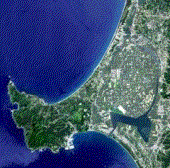
陸けい島・・・陸繋島(りくけいとう)とは、砂州によって大陸や大きな島と陸続きになった島のことである。海岸近くに島があると、沖からの波が島の裏側で打ち消しあい、波の静かな部分ができる。ここには沿岸流などで運ばれてきた砂が堆積しやすく、やがて海岸と島を結ぶ砂州が成長し陸続きとなる。
男鹿半島(秋田県)
ランドサット衛星写真
海食洞・・・海食洞(かいしょくどう)とは海岸段丘の地形によく見られる波浪の浸食による洞窟。 水面近くに形成される物は、干満の具合により、波が来るたびに海水を中の空気と一緒に吹き出す事がある。これを潮吹き穴と呼ぶ。
海食洞(潮吹き穴)
三重県大王崎
海食台・・・波食台と同じように考えてよろしい。
5の (2)のヒント
プレートの境界の種類
プレートの境界には,①拡がる境界,②狭まる境界,③すれ違う境界の3種類があります. 拡がる境界は,プレートが生産されて両側へ拡がっていくという生産および発散の境界で,マグマの上昇により海嶺がつくられています.あまり強くない地震が海嶺の中央部で発生します.
狭まる境界は,向き合って進行してくるプレートが接触するところで,一方が他方の下に沈み込んでいく沈み込み境界と,まともにぶつかって重なり合う衝突境界とがあります.沈み込みは海溝を,衝突は大褶曲山脈をつくります.狭まる境界では強大な圧縮力が働いて,強い地震が頻繁に発生します.
すれ違う境界は,水平移動するプレートが側面で接して横にずれ合うところで,ずれの力が地震を起こします。
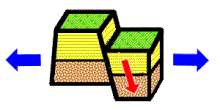
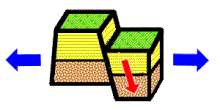
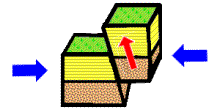
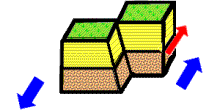

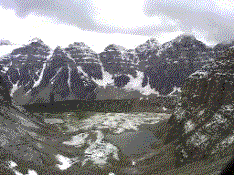
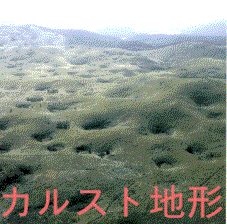

 天橋立(京都):砂州
天橋立(京都):砂州 ことで対岸またはその付近までに至ると、砂州と呼ばれる。
ことで対岸またはその付近までに至ると、砂州と呼ばれる。